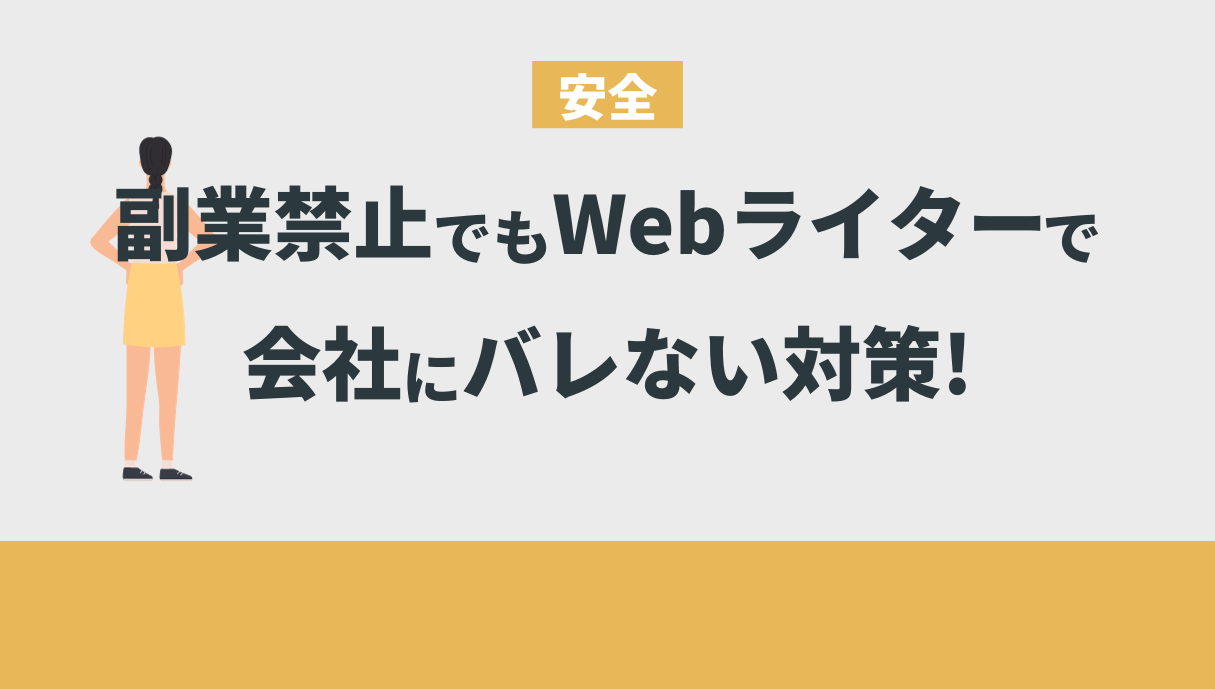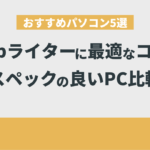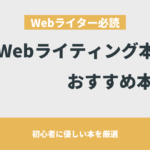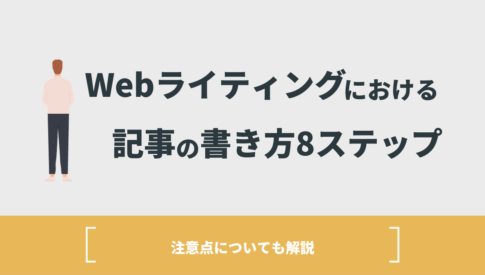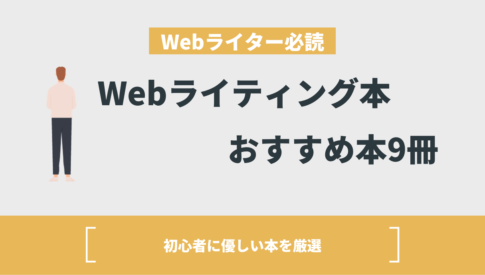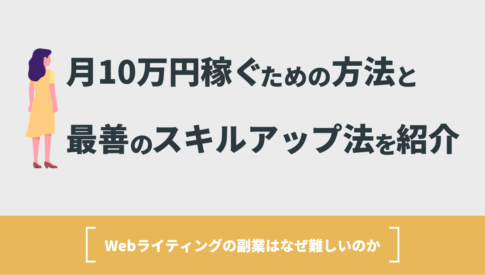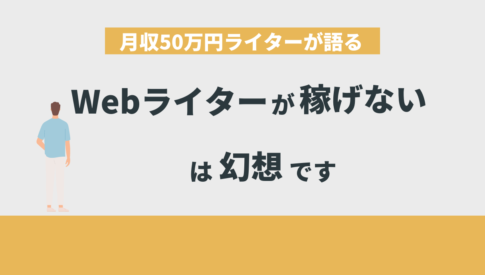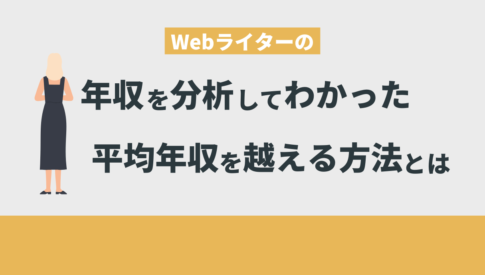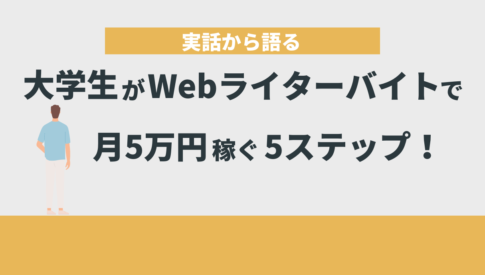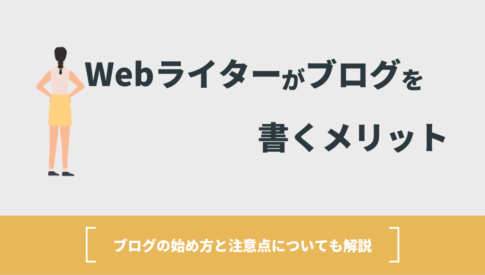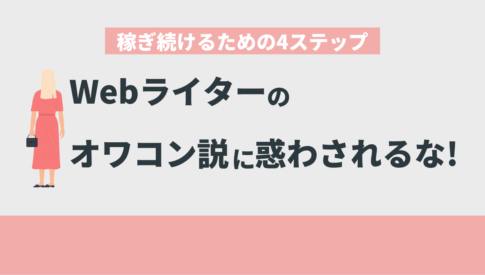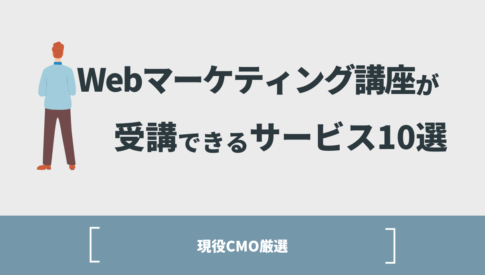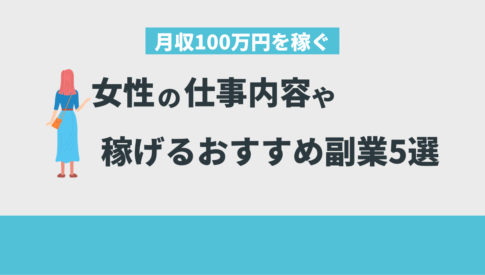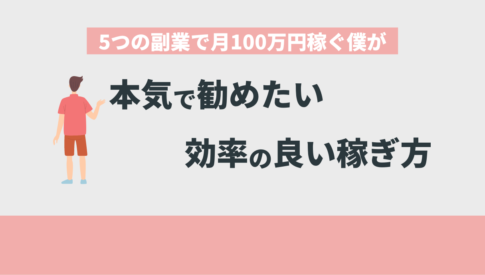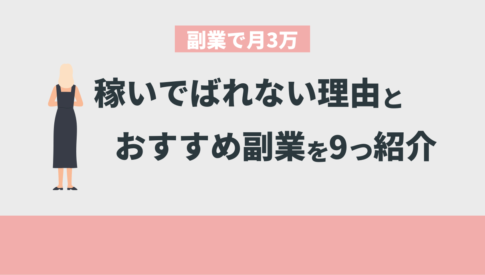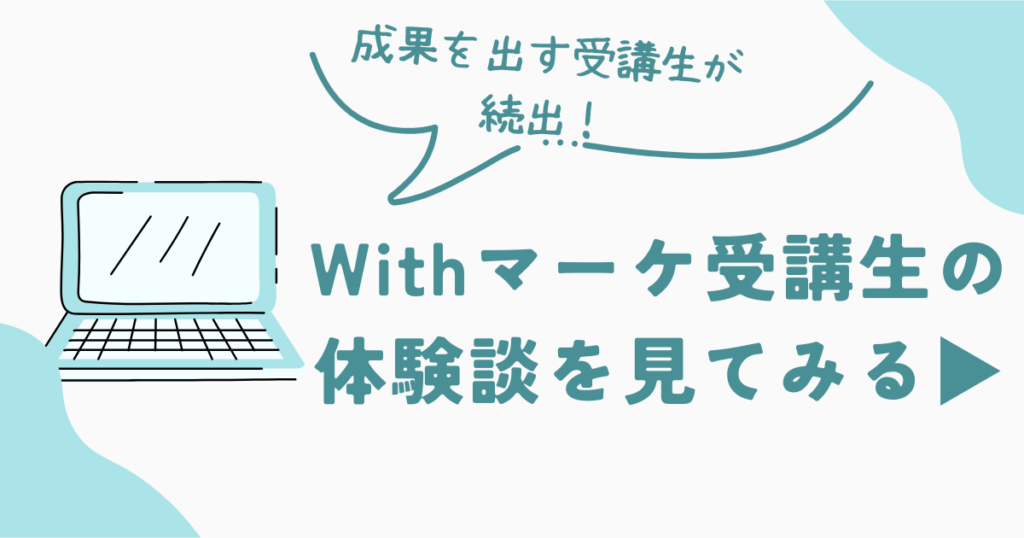副業禁止の会社に勤めながらWebライターの副業をするのは果たしてヤバいことなのだろうか…?
副業に興味があるものの、副業禁止の会社に勤めている方のなかには「どうにかして副業ができないだろうか…」と感じている方も多いでしょう。

会社にバレないかビクビクしながら副業をやりたくない方は、この記事を読んで何をすべきか明確にしましょう!
【前提】副業禁止でもWebライターとして稼げていなければバレない
大前提としてWebライターを副業で始めたとしても、年間20万円を超えて稼いでいなければ基本的にバレることはありません。

確定申告が必要になった場合でも、住民税の納税方法で「普通徴収」を選択すれば問題ありません。
- 納付書を用いて自分で納付する「普通徴収」
- 給与から直接天引きとなる「特別徴収」
普通徴収であれば、会社に住民税の変更が通知されないので、まずバレることはありません。
また、年間の収入が20万円以下であっても住民税の申告は必要になりますが、こちらも同じく「普通徴収」を選択すれば大丈夫。
ここまでの内容のとおり、副業でバレない方法は案外簡単です。

Webライターを始めたばかりの方にとって、年間20万円を稼ぐのは簡単ではありません。
そのため、これからWebライターを始めたい方や、既に始めているものの結果が出ない方は、ぜひ「Webライター無料5日間講座」を受講してみてください!
この講座では、Webライターとして月収5万円を稼ぐための方法が無料で学べます。
なかには、3ヶ月で月収10万円を超えた受講生もいるので、Webライターの副業で稼いでいきたい方は、ぜひ参考にしてください!
住民税でバレる金額であれば独立できるレベル
仮に確定申告や住民税の申告を誤って、住民税が変更されたとしても、正直なところ会社の経理担当者が気づくほどの金額ではありません。
仮に住民税で副業がバレるのであれば、それは独立を目指せるレベルに到達しています。

バレる前に辞めるというのも1つの選択肢です。
いまの仕事が嫌で副業を始めた方は、稼げればすぐにでも辞めたいと思っているのが本音でしょう。
そのような方には、スクールの受講がおすすめです。
「Withマーケ Webライティングコース」では、たった3ヶ月で高単価のWebライターが目指せます。
受講中に実際にメディアで掲載される実績作りが保証されていることに加え、案件獲得のサポート面談などもあるので、独立後も継続して仕事が取れるスキルが身につきます。
最短で高単価Webライターを目指したい方は、ぜひ受講してみてください!
また、下記記事では、厳選したWebライター講座・スクールを5つ紹介しています。
ぜひ、あわせてご覧ください!
参考記事:【最新版】Webライター講座・スクール厳選おすすめ5校を紹介
副業禁止の会社員Webライターでも副業はしてもいいのか
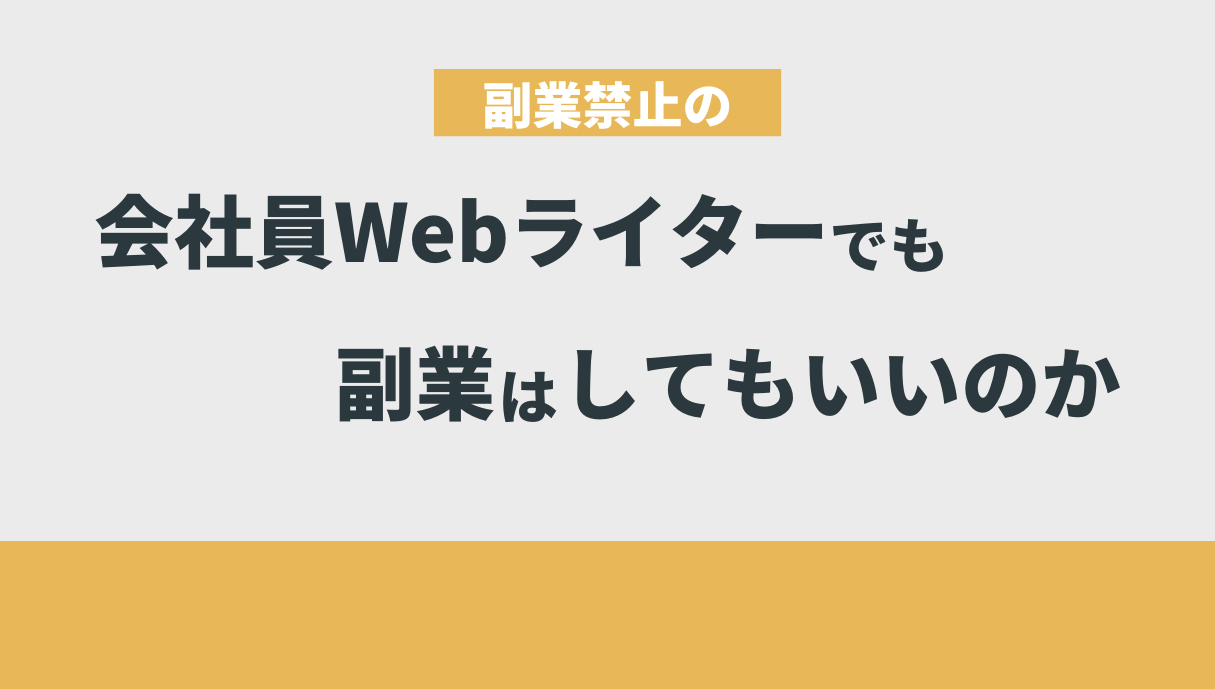
副業がバレない方法をお伝えしましたが、それでも心配な人は多いはず。

会社員の副業について、そのルールや万一バレた場合に起こりうるケースについて紹介していきます。
1.法律上は副業を禁止する規定はない
実は、法律上は会社が副業を禁ずる規定が存在しません。
つまり、会社員の副業は法律上何の問題もないということです。
日本国憲法第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する
引用元:e-gov法令検索
憲法にもはっきりと「職業選択の自由」について記されています。
会社員には仕事を自由に選択し決定する権利があるため、Webライターの副業をしても法律違反にはなりません。
中には、Webライターで副業収入を稼げたらとは思いつつも、会社が副業をNGとしているため実行に移せずにいる人もいるでしょう。
でもここまで解説したとおり、会社員の副業は、法律で認められていることをまずは認識しておきましょう。
2.副業禁止かどうかは就業規則が左右する
ではなぜ「会社が副業を禁止していてWebライターの副業ができない」などという事態が生じるのか、それは会社が独自に決める「就業規則」があるからです。
就業規則により副業禁止と定められていれば、それが会社のルールとなるため守る必要があります。
基本的には副業を行うことは認められている
近年の傾向としては、むしろ副業・兼業を促進する風潮が強まっています。
2018年1月に厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、「モデル就業規則」から副業を禁止する規定を削除したからです。
副業は基本的に推奨すべきであり、もしも企業が副業・兼業を制限するのであれば、以下の例に該当する場合のみであると書かれています。
- 労務提供上の支障がある場合
副業の業務が本業に差し支える(勤務時間など) - 業務上の秘密が漏洩する場合
副業をすることで社外秘の情報が漏れてしまう - 副業により自社の利益が害される場合
競合他社とのダブルワークにより自社に損害がもたらされる - 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
自社のオリジナル商品を他社でも販売する
つまり、上記に該当しない場合、会社が副業を禁止することは原則できません。
なお、副業が禁止とされるのは、次のように会社の不利益になる場合です。
- 副業に時間を割きすぎた結果本業に支障が出た場合
- 会社のブランドを失墜させた場合
- 故意に同業他社を選び副業した場合
勤め先の会社名を出したり、競合企業で働いたりする場合を除き、自己管理さえできていれば、基本的に上記には該当しないでしょう。
3.会社にバレた場合に罰則はあるのか
就業規則に副業禁止の項目が記されているのに関わらず副業をしたとして、万一会社にバレた場合にどのような事態が待っているのかについて把握しておきましょう。
会社にバレた場合の罰則については、会社に与えた不利益の度合いによります。
大きくは以下の5つの罰則に分けられます。
- 厳重注意
- 自宅待機
- 減給
- 降格処分
- 懲戒解雇
それぞれの罰則について見ていきましょう。
厳重注意
副業がバレても、その副業が本業に一切影響を及ぼさないものと判断されれば、厳重注意だけで終わる場合も多々あります。
近年の就業規則においては「届出をすれば副業は認められる」などのケースが増えていますが、この場合は規則に沿って届け出た上で堂々と副業を続けましょう。
自宅待機
厳重注意で済まない場合は自宅待機期間を設けられることがあります。
この待機期間中に事実確認などがおこなわれ、正式な処分が決定します。
減給
期間を設定し、その期間中の給料が減額される罰則もあります。
副業で稼いだ以上の金額をマイナスされるとそのダメージもかなり大きいため注意が必要です。
降格処分
役職者が就業規則を破り副業していたとなれば、その役職から降格させられるケースもあります。
先程の減給処分と似た処分ですが、降格+減給となるためこちらの方がペナルティとしては大きいです。
懲戒解雇
最も重い罰則が懲戒解雇です。
実際にあった事例を一つ紹介します。
このような、明らかに勤め先に対して不利益を与えた場合、懲戒解雇の対象となります。
Webライターとして副業をする場合、自社の機密情報を漏らすようなことさえしなければ、ここまで思い処分にはならないと考えて良いでしょう。
【副業禁止の会社員Webライターへ】副業が会社にバレない「2つの対策」
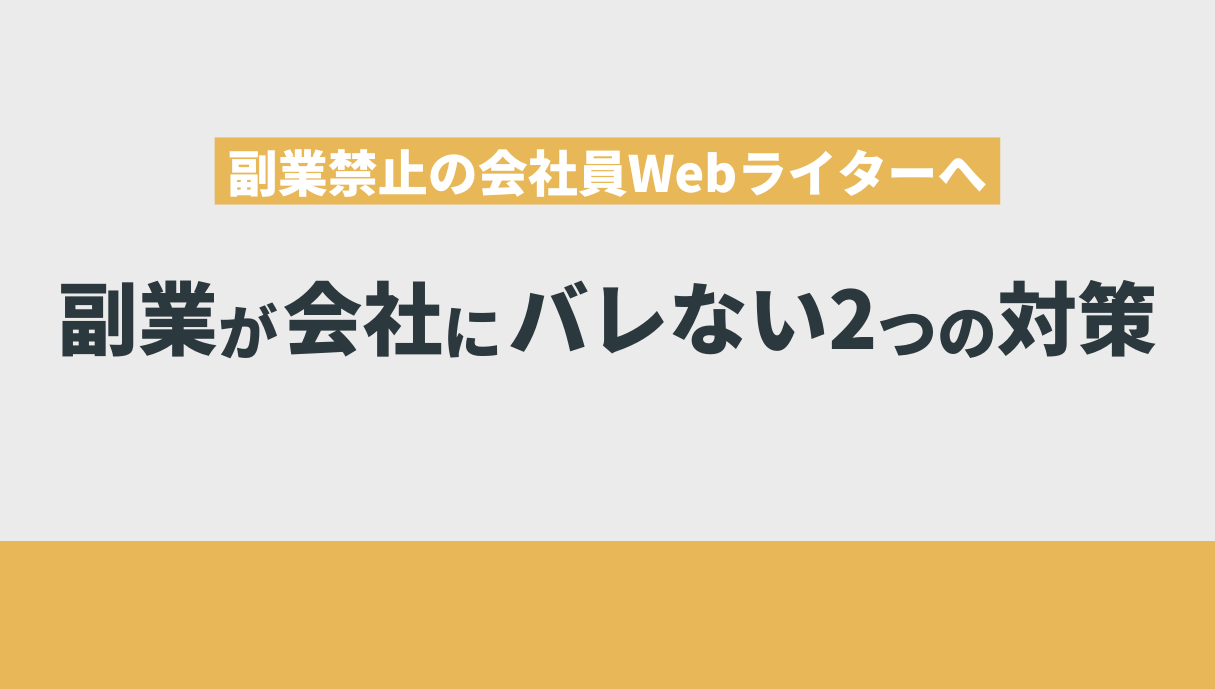
「Webライターの副業をしたい」「でも会社にはバレたくない!」という場合には、バレないように先回りして対策しておくことができます。
1.副業収入を年間20万円以下に抑える
冒頭でもお伝えしましたが、副業収入が20万円以下であれば、所得税を納める必要がないため確定申告は必要ありません。
確定申告が必要になるのは副業収入が20万を超えた時です。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
引用元:国税庁HP
20万を越えれば、上記の2もしくは3に該当するため、確定申告が必要になります。
逆に言えば、20万を超えなければWebライターとして得た収入については自ら口外しない限り、会社にバレることはまずないでしょう。
ここでもう一つ気をつけるべきは「住民税」です。
20万円を超えなければ確定申告の必要はありませんが、住民税の手続きは必要になります。
住民税の納付方法は以下の2つです。
- 納付書を用いて自分で納付する「普通徴収」
- 給与から直接天引きとなる「特別徴収」
住民税の手続き時に「普通徴収」を選んでいれば、会社にバレる心配はないと覚えておきましょう。
2.クラウドソーシングを利用する
クラウドソーシングはネット上で全てのやり取りが完結するため、会社に副業がバレにくい方法です。
国内最大のクラウドワークス公式HPには、その仕組みがこのように図解されています。

引用:クラウドワークス公式HP
上記のように、仕事を請け負う際に雇用契約を結ばないため、クラウドソーシングで得た報酬は給与所得には該当しません。
所得は「雑収入」として住民税を納付するための手続きを済ませる必要があります。
先程と重複しますが、納付方法は「普通徴収」にしておきましょう。
【副業禁止の会社員Webライターへ】副業がバレた際の「2つの対処法」
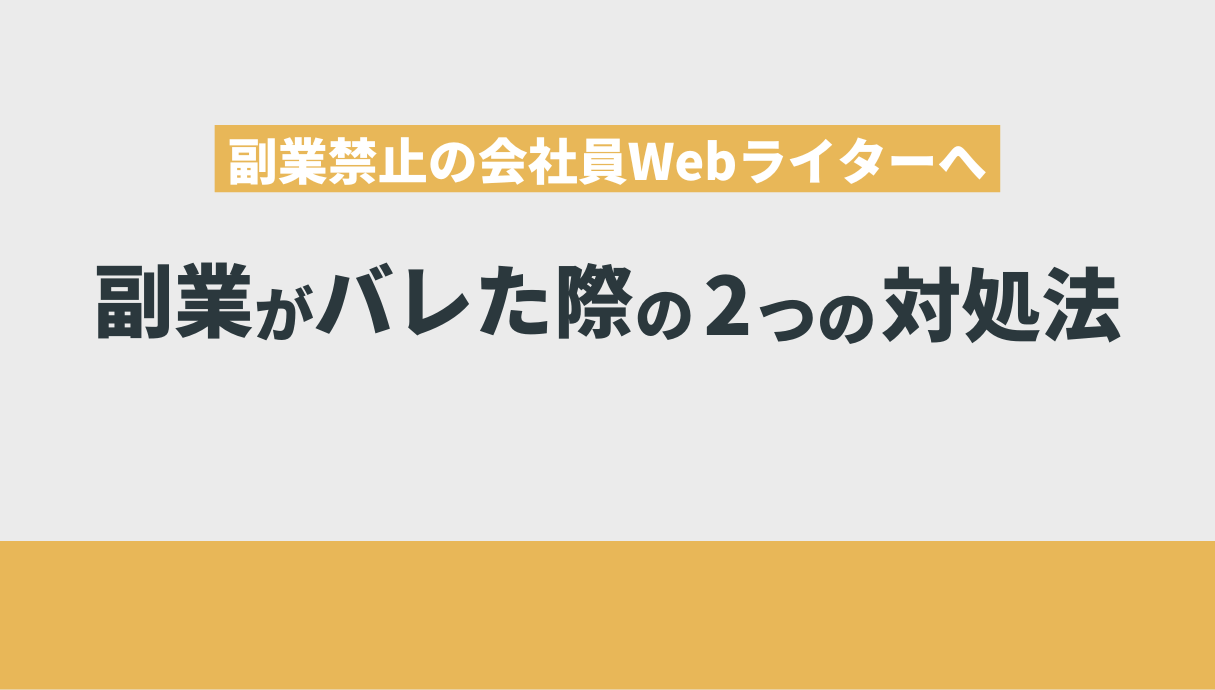
バレないように注意していても、会社にバレてしまう可能性は常にあります。
万一に備えてバレた場合の対処法についても知っておきましょう。
1.株や仮想通貨、FXでの所得だと伝える
副業で収入を得ていることが会社にバレたとしても、それがどのような収入なのかまでは把握できません。
そのため、副収入を得ていることがバレた場合は、「仕事を他にしている」のではなく「投資」で得た収入だと伝える方法があります。
投資は「副業」ではなく「資産運用」であるため、副業禁止の会社に勤めていても罰則に問われないからです。
Webライターの副業をしていることをわざわざ自分から会社に伝える必要はありません。
仕事でなく投資であることをアピールし、うまくトラブルを回避していきましょう。
2.罰則があまりにも重い場合には労働審判を利用する
副業がバレた場合の処分が極端に重い場合は労働審判という方法を利用することもできます。
- 労働審判手続は,解雇や給料の不払など,個々の労働者と事業主との間の労働関係のトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決するための手続です。
- 訴訟手続とは異なり非公開の手続です。
引用元:裁判所公式HP
労働審判でなく労働裁判を申し立てることもできるが、裁判となると第一審だけでも平均審理期間が14.3ヶ月かかります。
一方、労働審判は原則3回以内の期日で審理を終結させることができ、その迅速性が裁判とは大きく異なります。(ちなみに1回目から2回目、2回目から3回目の間隔は1〜2週間ほどだ)
また、裁判では代理人として弁護士を立てる必要がありますが、労働審判の場合、労働者のみでの手続きが可能です。
万一極端な罰則を課せられた場合には、労働審判という方法があることを覚えておきましょう。
公務員が副業でWebライターをやるのはお勧めできません
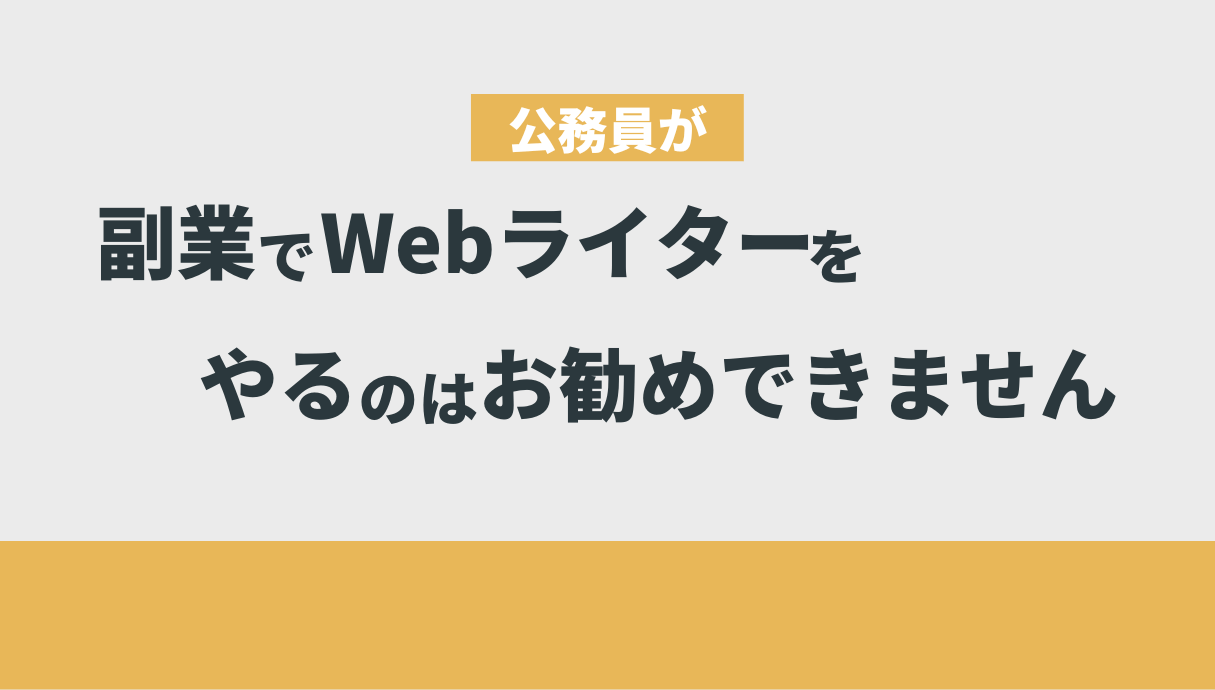
会社員の場合、副業をしても原則として問題ありません。
しかし、公務員の場合は副業自体が認められていないため注意しましょう。
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
引用元:e-gov法令検索
上記は国家公務員法と地方公務員法の罰則ですが、結局はいずれも「いかなるときも営利に関わってはいけない」と定められています。
そのためWebライターとしての副業もおすすめできません。
副業が基本認められているのはあくまでも会社員のみです。
まとめ
本記事では副業でWebライターになりたい、会社勤めをしながら空き時間で副収入を得たい方向けに、会社員の副業としてのWebライターについて解説しました。
副業NGの会社は確かに実在するが、近年ではかなり減少傾向です。
Webライターで副業をする際には、会社の就業規則を必ず確認しておくこと、そしてバレないための対策を徹底しておくことが重要となります。
※会社にバレるほど副業収入をまだ稼げていない方は、まずWebライターとして稼ぐための”正しい知識”を身に付ける必要があります。
安定的にWebライターで月5万円を稼ぐための『Webライター無料5日間講座』をご用意しているので、ぜひ受講してみて下さい!
また、下記記事では、厳選したおすすめのWebライター講座・スクールを5つ紹介しています。
「スクールや講座を比較して決めたい方」は、ぜひ参考にしてください!