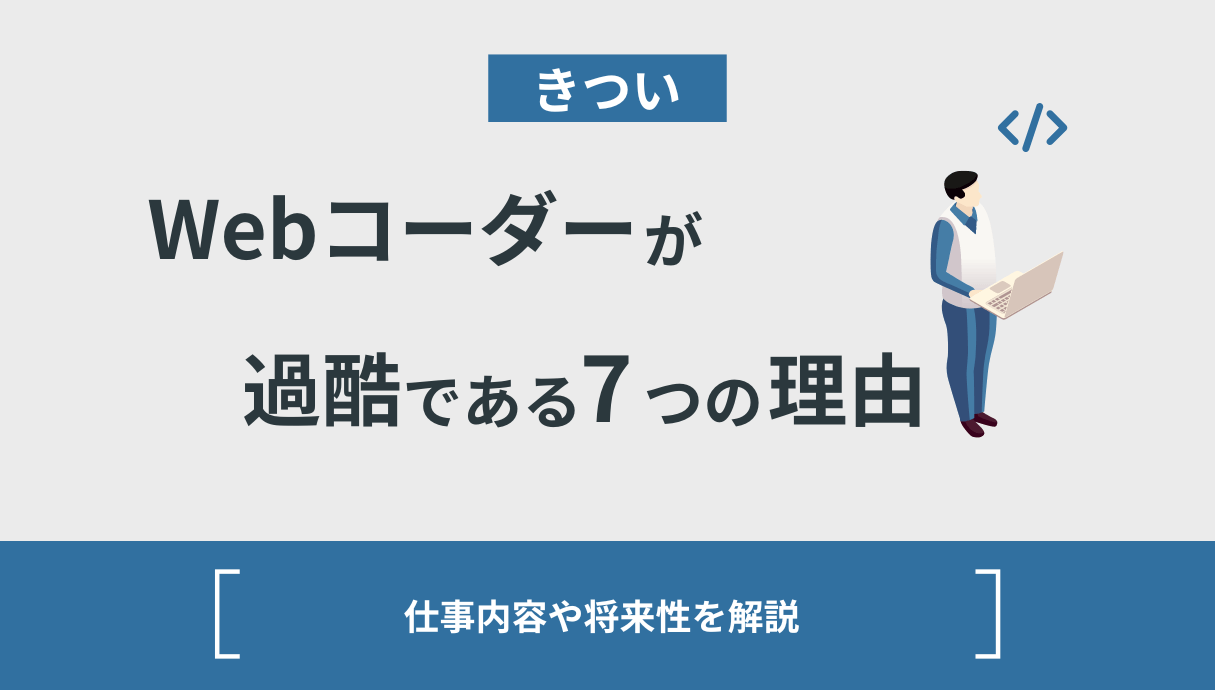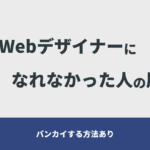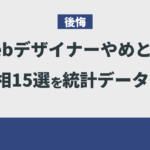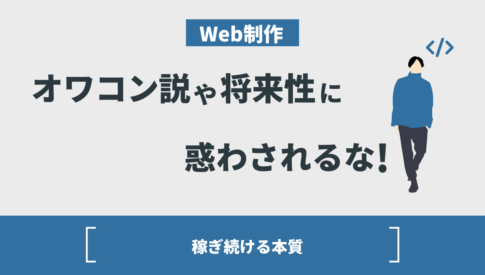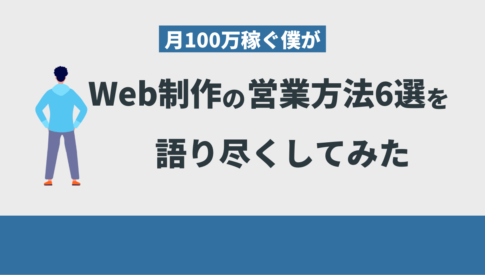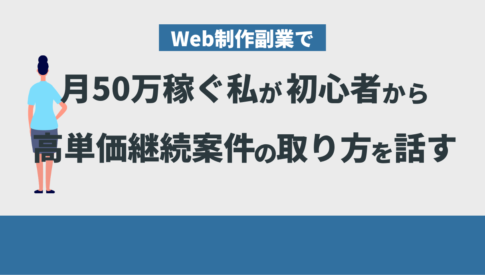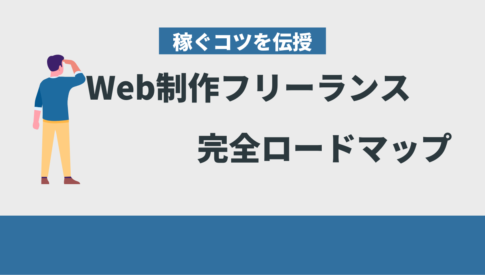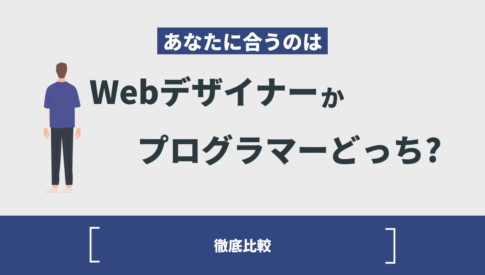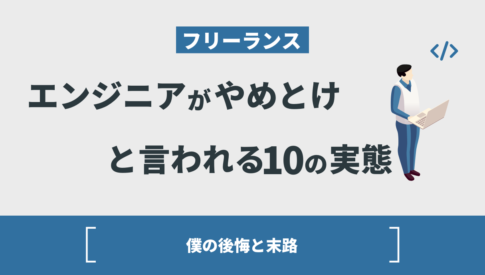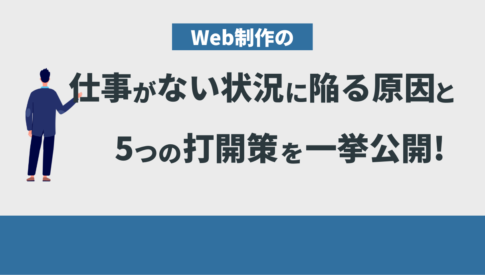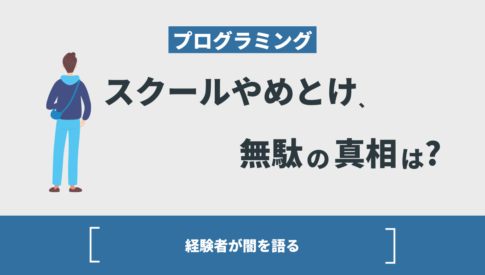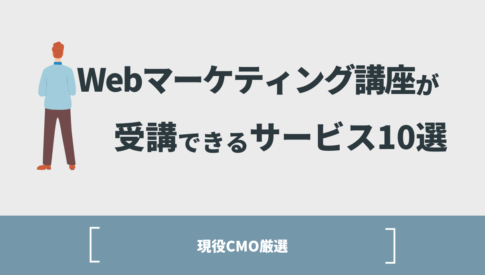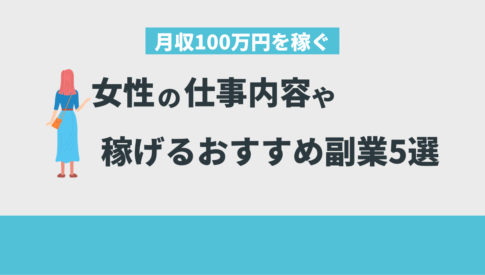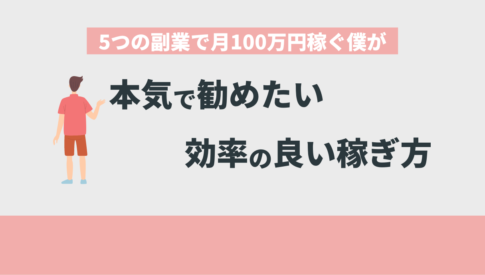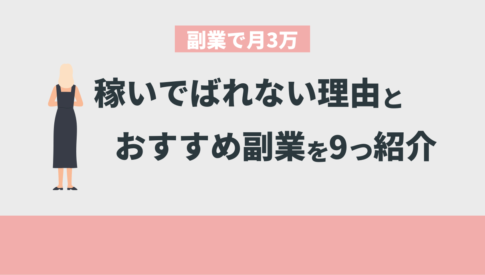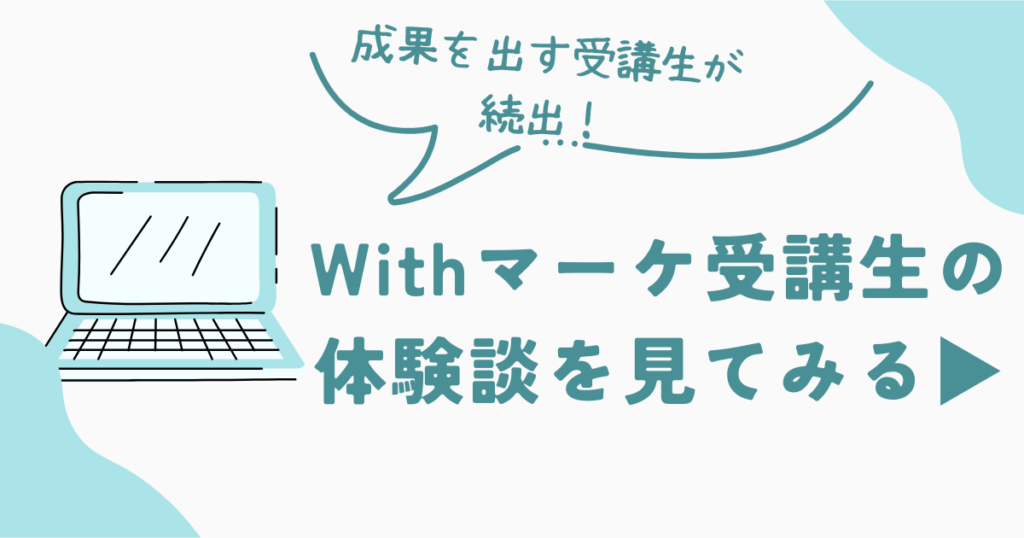Webコーダーがきついと言われる真相はシンプルで、稼げないからです。
もっと具体的に言うと、コーディングを身につけただけでは稼げないというのが真相。
実は、Webコーダーが仕事を貰って稼げるかは、コーディングスキルよりもあるスキルが関係しているのです。
ちなみに、「営業スキルを身につけた方がいいよ」と一般的な話をするつもりはありません。
本記事では、稼げるWebコーダーが1人でも増えるような内容になっているので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
Webコーダーはきついと言われる理由と対処法
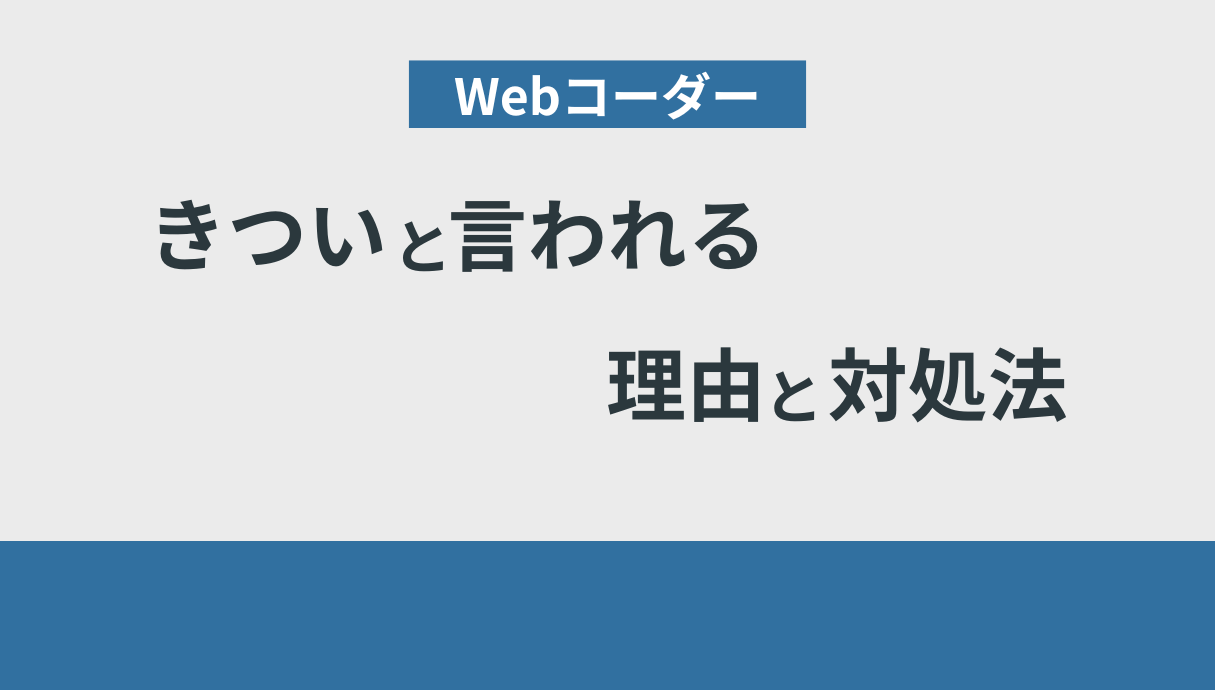
コーディングだけを身につけても稼げないから
コーディングだけを身につけた、Webコーダーは例外なく低収入です。
コーディング案件の平均単価といえば5〜10万円ほど。
しかし、多くのWebコーダーが1案件につき1万円を満たない単価で引き受けている現実があります。
自分自身の貴重な時間を割いているにも関わらず稼げないなら、バイトをやって着実に稼いだ方がマシじゃんと思ってしまいます。
ただ、稼いでいるWebコーダーもいる事実もあるのです。
そのため、Webコーダーはきつそうだから辞めとこうと思って諦めるのはまだ早いです。
仕事があって稼いでいるWebコーダーもいるワケ
稼いでいるコーダーは、朝から晩まで働いているのではなく高単価案件だけを抱えています。
しかも次々と依頼がくるので、生活に余裕が生まれ仕事を断ることも。
そう聞くと、「コーディングスキルやコネがあるんでしょ」と思うかもしれません。
しかし、コーディングのスキルが高いわけでもコネがあるわけでもありません。
ただ、ある仕組みを作ることに力を入れているだけなのです。
ある仕組みとは何かを、次で種明かししていきますね。
稼いでいるWebコーダーが実践している仕組み
稼いでいるWebコーダーが実践しているものこそ、マーケティングを使った仕事依頼が次々にくる仕組みのこと。
つまり、稼いでいるWebコーダーが実践していたマーケティングは、お客様に選ばれる仕組みです。
一見、マーケティングと聞くと「言葉だけでもう難しそう」と感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は、マーケティングでお客さまに選ばれる仕組み作りを分かりやすく5日間に凝縮してまとめました。
稼げるWebコーダーになりたい方は、ぜひ受講してくださいね。
Webコーダーが「きつい..」と言われる7つの理由
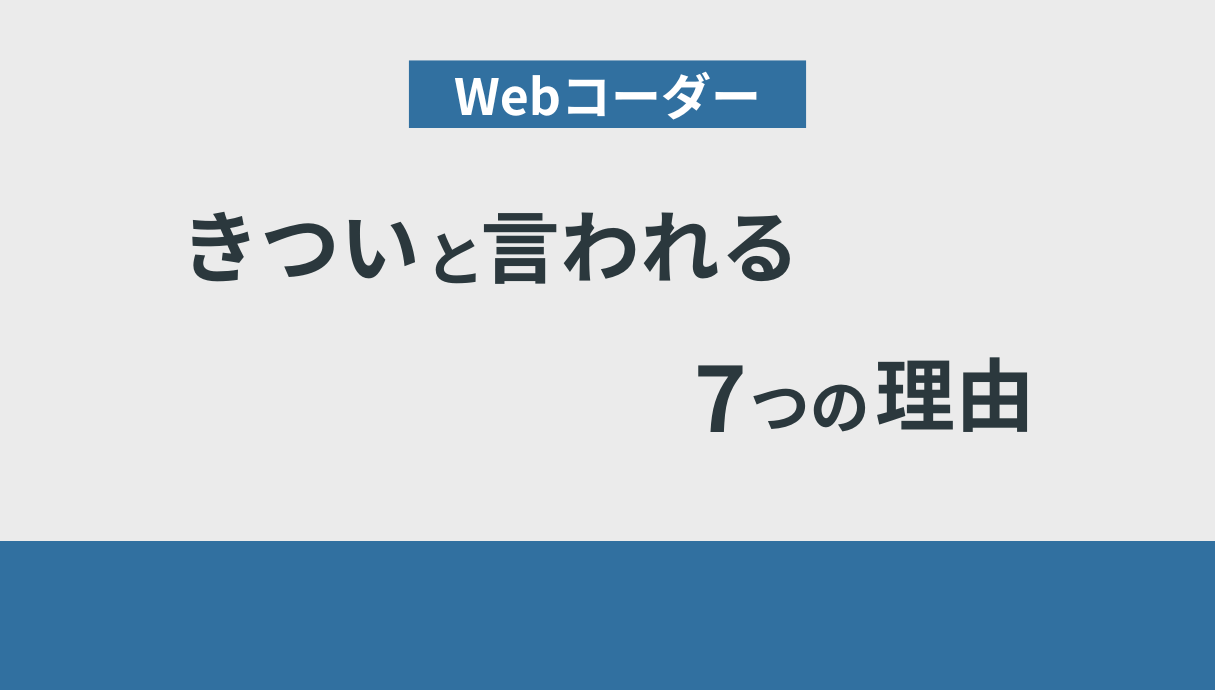
早速、なぜWebコーダーはきついのか?過酷な実態を詳しく見ていきましょう。
- 他のIT系の仕事に比べて年収が低い
- 下流工程の業務になりやすく、消耗しやすい
- スキル不足を感じやすい
- コーディングスキルの価値が下がっている
- 技術やトレンドの変遷に合わせて学び続ける必要がある
- ライバルが増えて、コーダーが飽和しつつある
- 先行き不透明で、将来性が怪しい
上記7つのきつい理由は、実際僕も全て経験しました。
それぞれ深掘っていきますね。
きつい理由①:他のIT系の仕事に比べて年収が低い
後ほど詳しく解説しますが、Webコーダーは他のIT系の仕事に比べて、稼ぎづらい一面があります。
僕がフリーランスWebコーダーとして活動していた頃は、未経験だったということもありますが、3,4日くらいかけた1案件につき1万円ほどでした。
ヒヤリングや修正などクライアントとのコミュニケーションも含めて、夜な夜な疲弊しながらやっていたので、時給単価にすると20円〜30円ほどだったかと思います。
きつい理由②:下流工程の業務になりやすく、消耗しやすい
Webコーダーの仕事はどうしても、理不尽なことが多かったり、修正が繰り返されたりと、何かと消耗します。
なぜなら、Webコーダーの主な仕事である「コーディング」は、Webサイトやアプリなどの作成過程において一番下流の工程だからです。
営業(案件獲得)したり、企画・立案などの要件定義をしたり、設計やデザインをしたりした後に、はじめてコーディングが行われるので、どうしても周囲の状況に左右されやすいのです。
きつい理由③:スキル不足を感じやすい
Webコーダーをしていると、今のままでいいのか… と自信のスキルに対して不満を感じてしまうときがあります。
Webコーダーの仕事は、Webデザイナーのようにデザインをすることもなければ、エンジニアのように設計やテストなどの複雑な開発業務をすることもないからです。
仕事内容は至ってシンプルなのですが、ずっとやっていると、それが返って将来に対する悩みの種となりうるのです。
きつい理由④:コーディングスキルの価値が下がっている
Webコーダーの主な業務である「コーディング」。
実は、近年新たに「ノーコード(NoCode)」と呼ばれる誰でも個人で気軽にWebサイトを作れてしまう便利なツールが普及したために、コーディングの価値が下がってきているのです。
そのため、コーディングに対するハードルは以前に比べてだいぶ下がってきており、競争が激しくなったり、単価が下がったりしつつあります。
きつい理由⑤:技術やトレンドの変遷に合わせて学び続ける必要がある
Webコーダーは、目まぐるしく移り変わる最新技術や業界のトレンドに追いつくために、日々勉強をし続けなくてはなりません。
基本、IT/Web業界は学び続けるのが当たり前なのですが、未経験からWebコーダーになった人にとっては「学ぶこと」を習慣化することに苦労するでしょう。
1年前に誰もが使っていたツールや言語が、今では使い物にならず、新しいもので仕事が行われるなんてことは日常茶飯事なのです。
きつい理由⑥:ライバルが増えて、コーダーが飽和しつつある
Webコーダーに転職する人は、年々増えており、競争率がこれまでになく激化しています。
無料で気軽にコーディングを学習できるサービスが普及していたり、プログラミングスクールが世の中に浸透してきたりしているのが大きな要因ですね。
ITの需要が高まるIT社会であるために、プログラミングが義務教育になったり、IT人材が増えたりすることが良いことですが、その分ライバルが増えることは避けて通れません。
きつい理由⑦:先行き不透明で将来性が怪しい
ノーコードのような画期的なツールが登場するなど、IT化が異常に速く進んでいる世界において、Webコーダーの行く末は不明確であり、決して安定とは言い難いです。
コーディングができる人が増えてきているので、仮にWebコーダーになったとしても、仕事として成立するのかどうか… 不安な人も多いはず。
Webコーダーの将来性に関しては、後ほどまた詳しく解説していきます。
そもそもWebコーダーとは?【仕事内容】
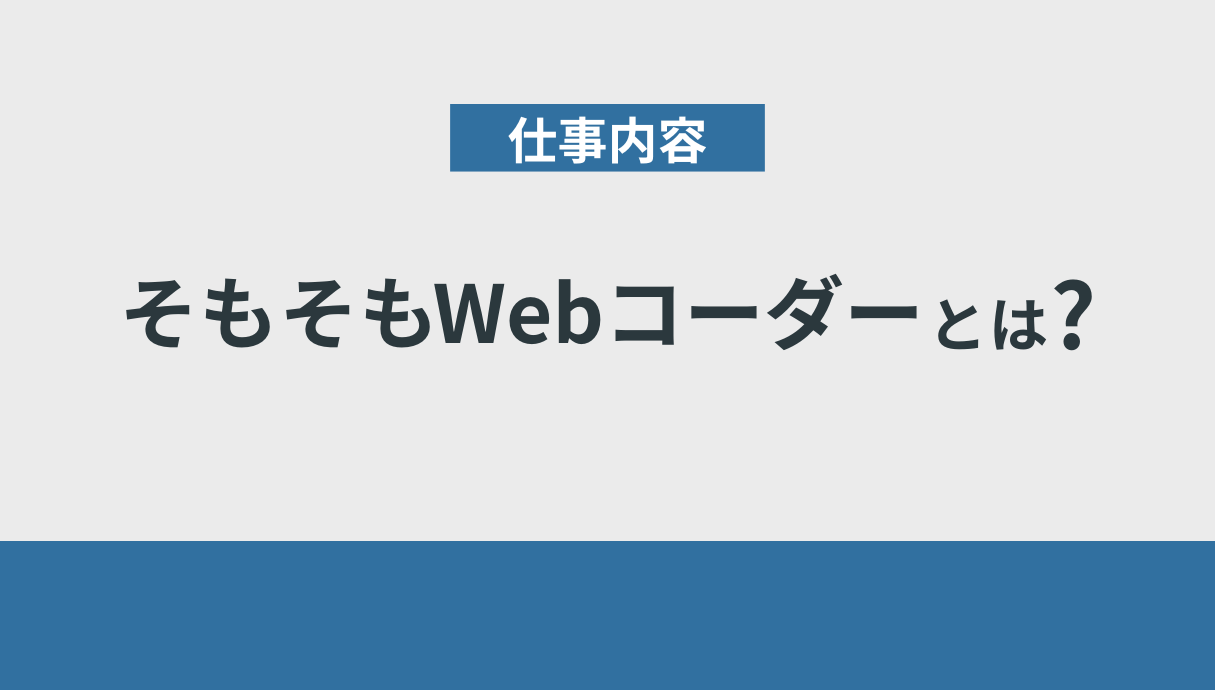
ここまで、Webコーダーがきついと言われている理由を7つご紹介してきましたが、そもそもWebコーダーとはどんな仕事なのでしょうか。
改めて、Webコーダーの定義から、未経験でもわかりやすく解説していきます。
Webコーダーの定義
Webコーダーとは、Web上のテキストや画像などの配置や、色・動きなどの見た目をコーディングによって整えて、Webページを作る仕事です。
コーディングでは、主にHTMLやCSSなどのマークアップ言語をはじめ、JavaScriptという言語やそのライブラリであるjQueryなどを用います。
そのため、「HTMLコーダー」や「マークアップエンジニア」と呼ばれることもあります。
少しややこしいのが、Webコーダーと似ている職種が沢山あることです。
「フロントエンドエンジニア」や「ソフトウェアエンジニア」、「Webデザイナー」など。
似ている「フロントエンドエンジニア」との違いは以下の通り。

フロントエンドエンジニアは、Webコーダーの業務内容に +αで設計や開発、カスタマイズ等、複雑な業務も担当します。
下記の図を見ると、それぞれ業務内容が重なっていることがわかりますね。

参考:Webデザイナーになるために最低限必要なスキルはなにか | Webと本 Webooke
上記の図で言うと、『コーディング』の箇所を主に「Webコーダー」が担っているという認識でいいでしょう。
Webコーダーの主な仕事内容・やりがい
Webコーダーの基本的な仕事内容は、ライターが作成したテキストや、デザイナーが作成したWebデザインや画像などのデータをもとに、それらを忠実にWeb上に表示させること。
非常にシンプルではありますが、SEO対策を意識したコーディングや、動作確認、情報更新・修正など、意外と業務内容は多岐に渡ります。
それでも、他の職種に比べると、取り組みやすい仕事でもあるので、副業としてやっている方も割と多い印象です。
やりがいとしては、コツコツと作業(コードを書くこと)を通じて、紙ベースや二次元のデザインがWeb上に形作られていき、自分のやったことが多くの人に見られることなどがあります。
何か与えられた課題に取り組んだり、単純作業をコツコツと続けるのが好きだった方は向いてるかもしれません。
一方、自分の好きなようにアイデアを出したり、課題ややり方を模索しながら物事を進めるのが好きだった方はマーケティングなどの企画職などの方が適しているかもしれないです。
Webコーダーの年収や将来性【きつい?】
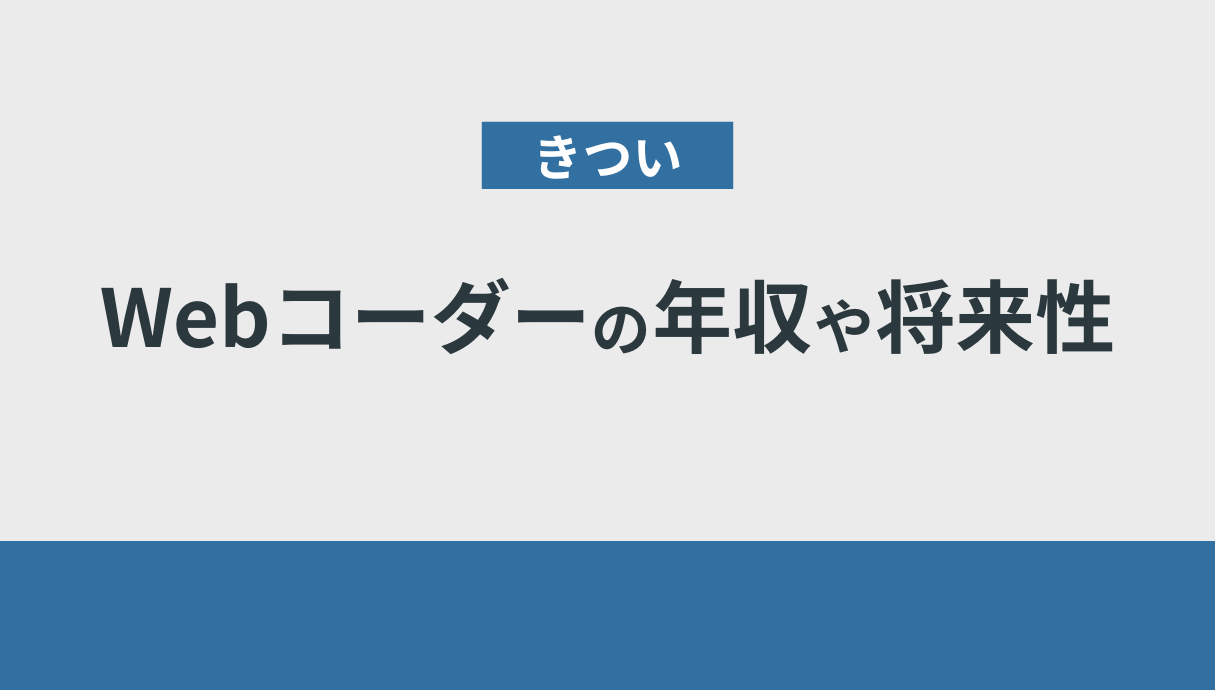
続いて、Webコーダーの年収や将来性など、気になる裏事情を暴露していきますね。
まずは、年収の方から。
Webコーダーの平均年収
Webコーダーの平均年収は「320万円」ほどと言われています。
他のWebコーダーと似ている職種と平均年収を比べると、以下の通りになります。

業務内容こそ似ているところがありますが、その中でもWebコーダーは比較的低い傾向にあるということがわかりますね。
案件単価の相場は、30,000円〜80,000円となっており、企業のコーポレートサイト(ホームページ)制作に関してはデザインも込みで200,000円となっています。

参考:クラウドワークス
やはり、「コーディングのみ」など、単一のスキルでできる案件は数が少ない上に、単価も低くなる傾向にある印象です。
”相場”は上記の通りなのですが、実際にクラウドワークスで案件を見てみると、相場よりも全体的に低いかなと感じます。
副業でやるにしても、本業としてやるにしても、コーディングスキル単体だと、仕事が大変な割にあまり稼げないという状況に陥っているようです。
Webコーダーの将来性
正直に言うと、コーディングだけをやり続けるWebコーダーの将来性は無いと言えます。
IT技術が進むにつれ、機械によるコーディングの自動化が進んだり、誰でも簡単にコーディングできるようになり、単純にコーディングスキルの価値が下がってきているのです。
今後ますます自動化が進むことが予想され、需要がなくなってくることはほぼ確実なので、今のうちに他のスキルも身に付けることをおすすめします。
機械に代替されないものは、アイデア(人間にしかできない柔軟な考え)ですよね。
それを存分に活かせるのは、単なる作業で終わらない「Webマーケティング」というスキルです。
何世紀も前から今〜この先もずっと無くなることのない『マーケテイング』について詳しくは、「5日間でWebマーケティング基礎が学べる特別無料講義」で知ることができますよ ↓
Webコーダーに向いていない人の特徴3選【適性なし】
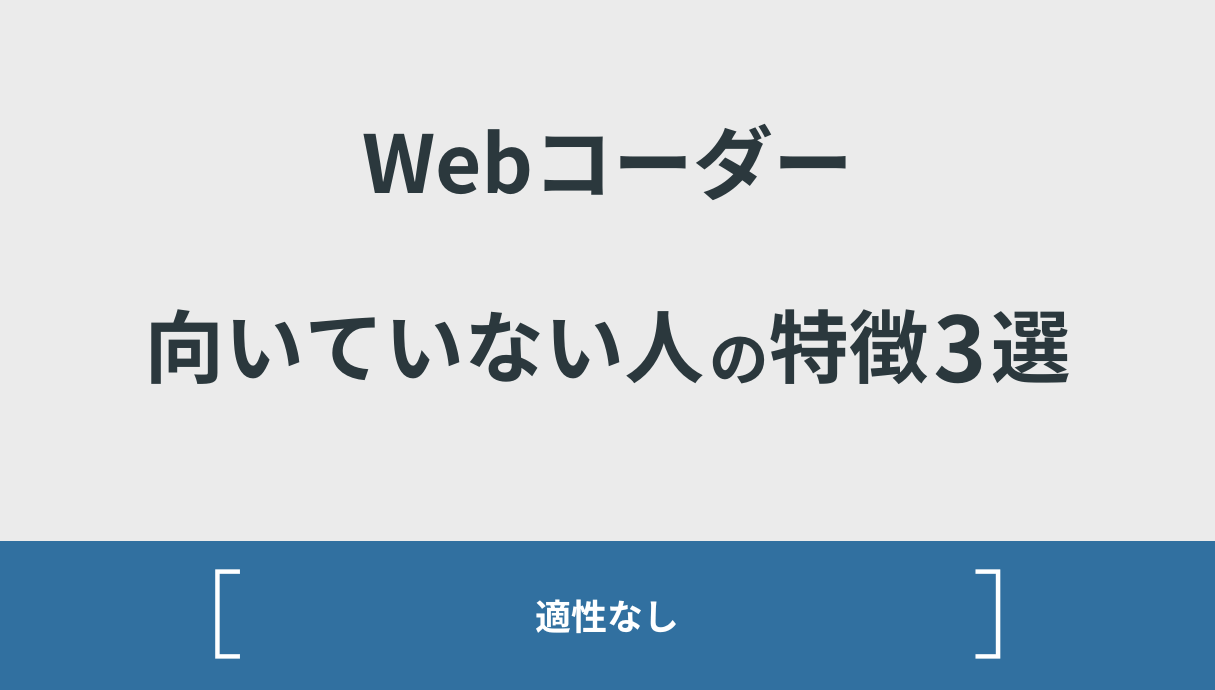
Webコーダーに向いていない人には、ある共通している特徴があります。
今回、その特徴を3つにまとめてお伝えします。
- 好奇心がない
- コミュニケーション力がない
- 主体性・行動力がない
これらに一つでも当てはまる方は、適性がマッチせずに、Webコーダーとして続けていくと苦しくなってしまうかもしれません。
向いていない人の特徴①:好奇心がない
まずは、Webコーダーに一番大切と言っても過言ではない要素である「好奇心」。
人は、好奇心があれば、新しいものに対して興味・関心を持てたり、常に学び続けることができたりします。
Webコーダーを含め、IT業界は目まぐるしく技術やトレンドが移り変わっていきますが、それに追いつくための学習が苦痛に感じてしまうと長くは続かないでしょう。
向いていない人の特徴②:コミュニケーション力がない
意外ですが、Webコーダー”こそ”、高いコミュニケーション力が求められるのです。
デザイナーやディレクター、クライアントなど、様々な人との擦り合わせにより、コーディングをしていく作業が非常に多い仕事でもあります。
誰とも話さず、自分のペースで働けると思っていては、現実とのギャップに打ちひしがれるでしょう。
向いていない人の特徴③:主体性・行動力がない
Webコーダーは、与えられた設計書やデザインをもとにコーディングをする仕事ですが、ただ受け身の姿勢で業務をこなすだけでは務まりません。
積極的な報連相はもちろん、コーダー目線や時には経営者目線の提案をすることが大切になってきます。
逆に、そういった自分からアクションを起こせる主体性や提案力がないと、この先Webコーダーとして食べていくのは難しくなっていくでしょう。
未経験から”稼げる”Webコーダーになるために必要な3つのエッセンス
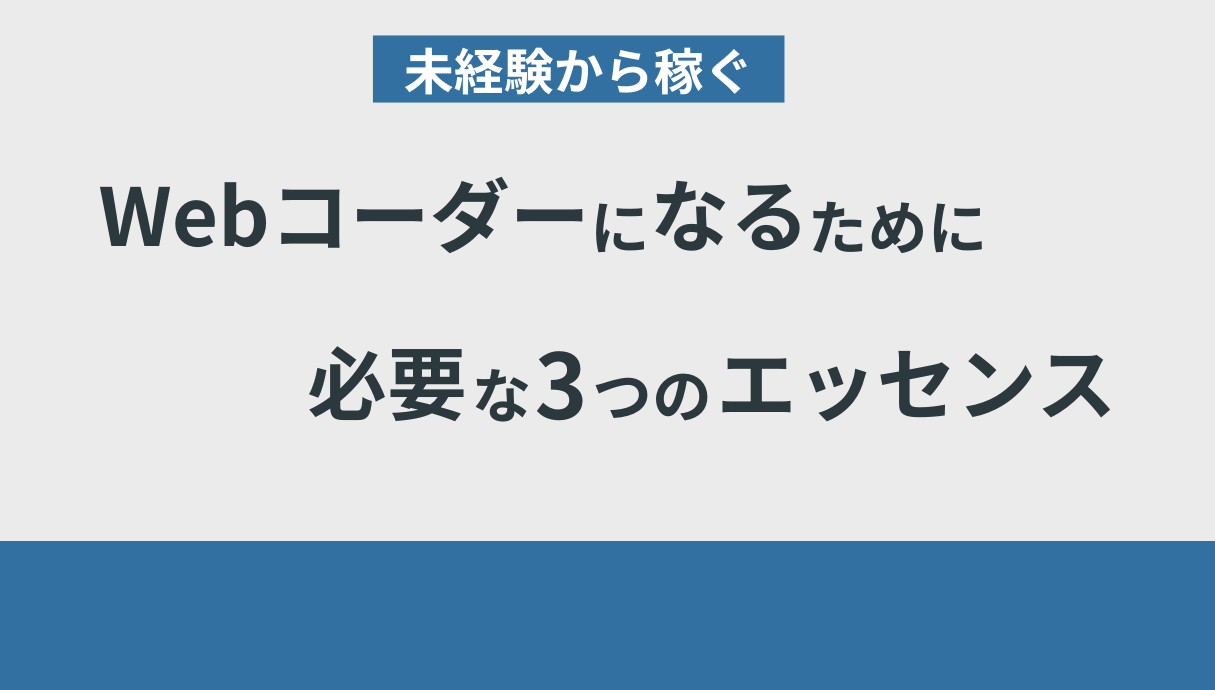
最後に、「誰でもコレを意識すれば未経験からでも稼げるようになる!」という本質的な心持ちを3つご紹介していきます。
- 「コーディングは売上を上げるためにやる」という認識
- 「常に自分の価値を高め続ける」という気概
- 「なるべく手を動かさないことが美徳」とする意識
これらを押さえれば、必ず長期的に稼ぎ続けることのできるWebコーダーになれるので、ぜひ一つ一つ胸にしまっておいてください。
エッセンス①:「コーディングは売上を上げるためにやる」という認識
一つ目は、何のためにコーディングをするのか?というところ。
多くのWebコーダーは、特に目的意識を持たずに目の前のタスクをこなしていますが、それではなかんか稼げないのが実情です。
本当に、継続的に稼いでいきたいのであれば、今日からコーディングの目的を『クライアントの売上を上げるため』という認識にすり替えてください。
実際、企業は自社の売上を増やすために、集客をWebサイトに頼っており、コーディングはその企業の顔となるWebサイトの作成を担っているわけです。
逆に言えば、どうすれば売上を上げられるのか?というマーケティング思考を持ったWebコーダーは、クライアントに提案をすることができ、売上に貢献できるのです。
エッセンス②:「常に自分の価値を高め続ける」という気概
二つ目は、どういった態度で普段の仕事に取り組んでいくか?というところ。
近年、ITを取り巻く環境は凄まじい速度で変化しており、ずっと同じ技術内容・技術レベルで仕事をしている人は取り残されている状況です。
そんな中、生き残っていくため、もっと言うと「選ばれ、稼ぐため」には、他のWebコーダーさんよりも魅力的なポイントがないといけません。
そこで一番重要になってくるのが、進化し続けられるかどうか?というところです。
一見、稼ぐためにスキルを磨くというのは、自分よがりに思えるかもしれませんが、実際にはクライアント側も大きな恩恵を得ているのです。
企業からしたら、より難しい開発やサービスを実現するためにも高度なスキルが必要であるため、常に成長していて将来性のあるWebコーダーさんに、今後もお願いしたくなりますよね。
単一のスキルだけでなく、複数の周辺スキル(WebマーケティングやWebデザインなど)もマスターしているWebコーダーは、もう引っ張りだこで高単価案件を選べるようになるでしょう。
エッセンス③:「なるべく手を動かさないことが美徳」とする意識
三つ目は、どんな風に働くのがカッコいいのか?というところ。
たくさん手を動かして働いている自分を美化して、とにかく作業に時間や労力を注ぎ込み続けている人が多いですが、それは消耗するだけです。
Webコーダーの最終ゴールとして目指して欲しいのが「手を動かさなくとも、自動で仕事が回る仕組みを作ること」。
この目的があれば、必然的に学ぶことが変わってきますね。
直近はコーディングスキルだけでやっていけそうですが、10年先、20年先と長期的に見ると、間違いなく手を動かさなくとも稼げるスキルが必要になってきます。
例えば、集客スキルやマネジメントスキル、ディレクションスキルなど。
そして、それらを一気に学べてしまうたった1つのスキルが存在します。
それが『Webマーケティング』です。
Webマーケティングを習得すると、「待ちの営業」ができたり、自分のビジネスができたりして、お金も時間も潤うようになります。
もう消耗したくない!という方は、下記の無料で視聴できる「5日間講座」を体感してみてください↓
まとめ:Webコーダーがきついなら、もう少し視野を広げてみよう!
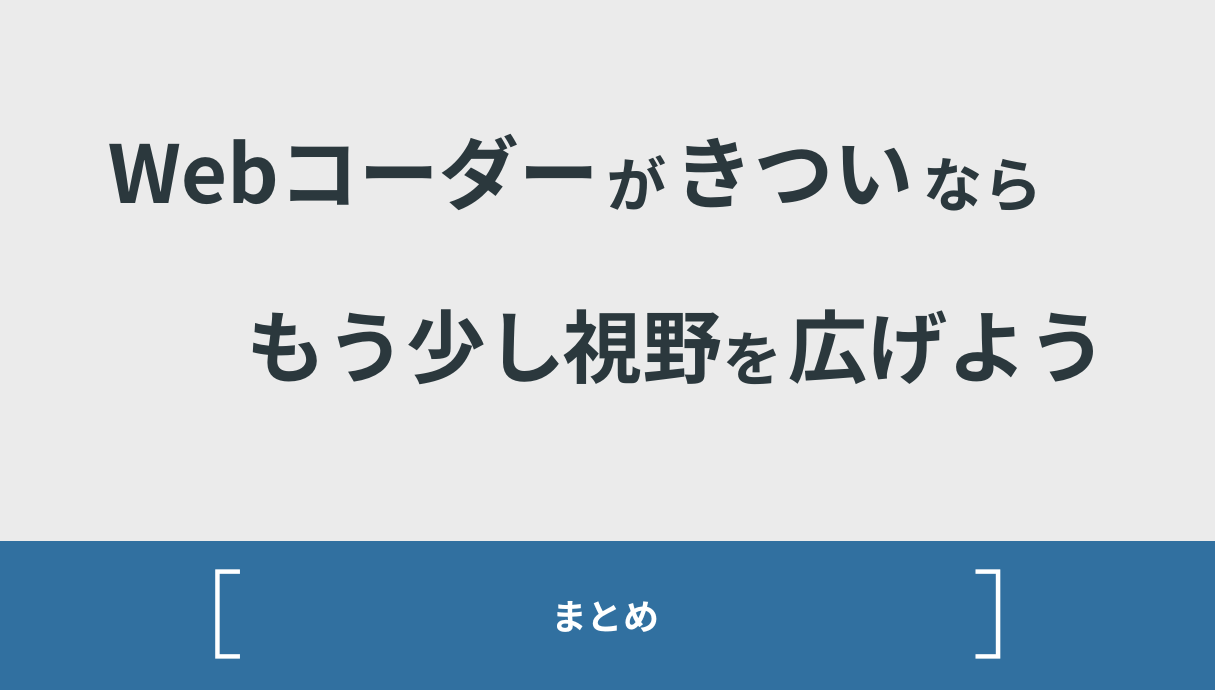
本記事では、Webコーダーが「きつい..」と言われる7つのポイントや、平均年収・将来性などの気になる裏事情をお伝えしてきました。
この記事で一番伝えたいのは、
ということでした。
コーディングなどのWebサイトを作れるスキルと非常に相性の良い『Webマーケティング』の全体像や基礎知識を、今なら無料で学ぶことができます。
「5日間の無料講座」が気になる方は、下記のボタンから詳細を確認してみてください!↓