「就活が本格化しているのに、SPIが全く解けない…」
「SPIができなくて、書類の段階で落とされてしまう。。」
大手企業を中心に、多くの企業がSPIの受験を課しているので、SPI試験が全く解けないと、とても焦りますよね。
実際に「最も頭を悩ましている就職活動の内容」によると、「筆記試験とSPI対策」が3位で多くの就活生の悩みの種になっています。
▼最も頭を悩ましている就職活動の内容
| 順位 | 項目 | 割合 |
| 1位 | エントリーシート対策 | 約34% |
| 2位 | 面接対策 | 約28% |
| 3位 | 筆記試験とSPI対策 | 約13% |
参照元:「最も頭を悩ましている就職活動の内容」を元に作成

ただ、実は、SPIが全く解けなくても、意外と多くの企業において、面接に進むことができ、内定を貰うことも可能です。
本記事では、SPI対策の方法を話し質も、全くSPIが解けない就活生が、「SPI無しでも優良企業1日でもから内定を貰う方法」を詳しく解説していきます。
意外と知られていない方法ですので、焦っている友達などにもぜひ教えてあげて欲しいです。
【結論】SPIが全く解けないなら、裏ルートを使えばいい
今から、SPIが全く解けない人にとって「残念なお知らせ」と「朗報」の2つがあります。
まずは、残念な悲報からお話ししましょう。
【悲報】SPIの学力試験の対策は、1.5〜3ヶ月はかかる
改めてですが、SPI試験は基礎学力などを図る目的で、大手企業が中心となって、選考に導入しています。
特に、人気がある企業ほど、SPI試験を導入しているところが多く、かつ全体の上位10〜20%ほどでないと、落とされてしまうことも多いようです。
また、SPI試験は、対策にある程度時間がかかります。元々受験勉強やテストが得意だった人を除くと、「高い点数を取るためには、1.5〜3ヶ月の対策は必要である」というの僕の実体験になります。

そのため、2024卒で、今から「SPI試験の点数を大幅に上げたい」と思う方は、SPIの対策は半分諦めた方がいいかもしれません。
「”半分諦めた方がいい”」というのは、期待しすぎないという意味です。もちろん、できるならば対策は続けて欲しいですし、人によっては点数も上がるでしょう。
しかし、人気企業のSPIのボーダーラインを超えるためには、かなりの点数が必要となります。
そのため、SPIの対策は50%ほどの力で行い、「そもそもSPI対策をせずとも、面接に進める優良企業」を探すことに残り50%の力を使った方がいいです。
【朗報】SPI試験を実施していない優良企業をたくさんある
ここからが朗報であり、SPI試験にてこずっている就活生や、まだ内定がゼロの就活生が必ずやるべきことです。
結論ですが、SPI試験を実施していない優良企業は意外とたくさんあります。

一部適性検査などはあったものの、僕が内定をもらった外資系コンサルティングファームや、30歳で年収1,000万を超える大手商社は、SPIは実施しておらず。
その他、内定をもらった、メガベンチャーやITスタートアップに関しては、いきなり面接に望むことができたんです。
僕自身の経験を踏まえると、SPIが苦手なのであれば、SPI試験を実施していない優良企業を受けた方がいいと言えます。
また、仮にSPI無しで内定をもらった企業が、志望している企業でなかったとしても、内定が一つでも貰えていれば自信に繋がります。
だから、あなたは「ストレス溜めて、SPI試験に手こずっている場合ではない」のです!
SPI試験を実施していない優良企業はエージェントを使えばすぐ見つかる
では、どうやって「SPI試験無しでも、内定がもらえる優良企業」を見つけるのか?
結論としては、就活エージェントなどのプロの力を使うといいです。
就活エージェントを使うことで、SPI試験を受けなくても、人柄が企業とマッチし、志望度が高ければ、人気優良企業の選考に即進むことができます。
エージェントによっては、登録後、数週間で内定をもらえることも多いです。
例えば、エージェントを使えば、下記全てをサポートしてくれます。
⬇︎就活エージェントがやってくれること
- 自分の希望に合う、優良企業だけをピックアップしてくれる。
- 多くの紹介企業は、ヘビーなSPIや書類選考が必要ない
- 基本的には評判の悪いブラック企業は紹介されない。なぜならエージェントにとっても信用が大事なため。
- あなたの自己分析を手伝い、あなたに合いそうな業界選び・分析をサポートしてくれる
- エントリーシート作成、面接対策など、内定に向けて必要なことを手伝ってくれる→結果として、就活エージェントを使えば、数週間〜1ヶ月で、内定をもらえることも多いです。

個人的におすすめなのは「MeetsCompany」というエージェントで、僕自身もお世話になりましたし、僕の後輩もMeetsCompany経由で、メガベンチャーから内定をもらっています。
色々サポートしてもらえて、無料なら使わない理由はないはずです!ぜひ、企業選びのためにエージェントは活用してみてください!
毎年多くの就活生に利用されているほど大人気で、すぐに日程が埋まってしまうので、今すぐ予約を確定しましょう! ↓
SPIが全く解けない原因を3つ紹介【どうしても突破したい人向け】
ここからは、「どうしても就職したい企業にSPI試験がある」という人向けの内容です。

SPIが全く解けないと嘆いている就活生は、ここを見れば解けない原因がわかると思います。
僕自身も、就活終盤では、SPIの通過率が高まりましたが、うまくいかなかった原因を3つ紹介します!
1.受検形式ごとの対策ができていない
SPIには3つの受検形式があり、それぞれの特徴を把握せずに受検すると本番で焦ってしまい解けないなんてことが生じます。
以下で、SPIの受検形式と特徴をまとめたので、確認しておきましょう。
- Webテスト
自宅のパソコンなどを使って受検することになります。
試験では、1問に対する制限時間があり制限時間が過ぎると次の問題に移っていく仕組みになります。
受検者の正答率によって出題される問題の難易度が変化していく形式です。
他の形式と異なって、電卓を使用することが可能になっています。 - ペーパーテスト
マークシートで回答していく方式になり、電卓を使用することがは認められていません。
他の形式と異なって、全体の問題を確認してから解くことができるので、時間配分をしやすい点があります。
- テストセンター
指定された会場のパソコンで受検し、1問ごとに回答時間が定められていて回答時間が過ぎていくと次の問題が出されます。
ペーパーテストより出題範囲が多いのと、1度解いた問題に戻ることができません
電卓を使用することはできなく、会場でもらう計算用紙を使用して計算していくことになります。
そして、1年以内であれば結果の使い回しができるようになっています。
しかし、SPIの点数を知ることができないので、自分の自身のあったものを企業に提出するかありません。
このように、3つの形式は共通する部分もありますが、3種3様で違った側面もあります。
例えば、電卓が使えるか使えないかで、計算に対してのスピードも変わってくるので、それぞれの受検形式に合った対策をしてく必要があります。
2.一問に時間をかけすぎて時間配分ができていない
SPIの試験問題は、問題数に対しての制限時間が非常に短いです。
1問に時間をかけすぎると、回答時間があっという間に終わってしまい、最終的に全然解けなかったとなってしまいます。
ここで、問題数に対してどのくらい回答時間があるか見てみましょう。
▼SPIの問題数と制限時間
| テスト形式 | 非言語 | 言語 |
| Webテスト | 20問(20分) | 41問(12分) |
| ペーパーテスト | 30問(40分) | 40問(30分) |
| テストセンター | 能力検査35分 | |
このように、時間に対しての問題数が多いことが分かると思います。
うまく問題を捌いていくためには、1問に囚われすぎるのではなく時間配分をしていくことがSPIを解く鍵になっていきます。
3.問題演習の量が足りていない
SPIの問題は、例年問題の傾向は変わりません。
そこでSPIを解くにあたって、問題に慣れて問題の傾向や問題の解き方を知ることが重要になっていきます。
しかし、1回ぐらいの問題演習の量では、問題の傾向や問題の解き方を把握したり理解することは不可能に近いです。
そのため、問題集を1周したから満足して解けるとは思わず、問題集を繰り返し行い完璧に理解できるまで解きまくることが大事になります。
【24卒は急げ】3月中にSPIの突破率を高めたいならこれをやれ
どうしても、SPI試験を突破する必要のある2024卒の就活生は、やはり急いだ方がいいです。
とはいえ、対策するにも時間がない、、何をしていいかわからない、、
このような現実があるならば、キャリアチケットスカウトを使うといいでしょう。
キャリアチケットスカウトは、プロフィールを登録しておくと企業からオファーの届くスカウトアプリですが、SPI試験の対策を効率よく行えるアプリでもあります。
というのも、SPI試験は、問題を解く試験があるのに加えて、適性検査などもあるからです。
そして、この適性検査も慣れておかないと、意外と時間がかかりますし、下手をすると、慣れていなかったというだけで落とされてしまいます。
そのため、キャリアチケットスカウトを通じて、自己分析や適性検査などの対策もしておくといいでしょう。
キャリアチケットスカウトは、iPhoneなどで使えるアプリで「自己分析サポート」と「企業からのスカウト」が無料で受けられます。
ぜひ、使ってみてください!
SPI言語分野を解く3つのコツ

SPIの言語問題で悩まされている就活生は多いので、SPI言語分野を解く3つのコツを理解しておきましょう。
1.語彙力を増やす
言語分野では、語彙力を試されるような問題が数多く出題されるため、知らない語彙ばかりだと解けないといったことが生じます。
実際に、どのような言語問題が出題されるか一部の出題例を見て把握しましょう。
▼語句の意味の出題例
【Study_Pro】(SPI).png)
参照元:「SPI無料学習サイト」
このように、語句の意味をそれぞれ知らないと解けず、当てずっぽで答えることになってしまいます。
そこで、語彙力を増やすには文章に慣れたり、SPIの問題集などを解いてよく見かける熟語や知らない熟語を覚えていきましょう。
1つ注意点として、出てきた語彙の意味だけを覚えるのではなく、反対語と類義語も一緒に覚えると語彙の幅も広がっていくのと効率もいいので合わせて確認しましょう。
2.長文問題に時間を残しておく
SPIは、制限時間に対しての出題数が多いので、長文問題と比べてサクッと答えられる問題に時間を取っていたら長文を解く時間がなくなってしまいます。
その結果、本来取れていた点数を落とすといったことが生じてしまいます。
以下で、どのくらい問題数に対して制限時間があるのか見てみましょう。
▼非言語分野の制限時間と問題数
| テスト形式 | 言語 |
| Webテスト | 20問(20分) |
| ぺーパーテスト | 30問(40分) |
| テストセンター | 非言語・言語合わせて(35分) |
確かに、制限時間の割には問題数が多いですね。
さらに、長文問題では文章の全体を読んで理解しないと答えられない問題が出題されます。
問題例が以下のような感じです。
- 抜けている1文をどこに入れるか
- 接続詞を入れる
- 本文と合致するもの
長文に時間を残すために、誤答率を図っているわけではないので、他の問題でわからない問題があった場合は、瞬時に答えましょう。
もしくは、適当にマークして、長文を解く時間に余裕を持たせましょう。
3.間違えた問題をメモしておく
言語分野では、解き方のコツや語彙を知っていると答えられる問題が多いので、間違えた問題を復習しておくと効率良く点数を上げることができます。
人間はすぐに忘れてしまう生き物なので、一度間違えた問題をそのままにしていたら、本番のSPIで出題されたとしても解けるなんてことはありません。
そうなると、一度解いたことがあったのに解けなかったら悔しいですよね、
しかし、問題を解いたことだけに満足してしまい、復習しないで次の新たな問題を解いてしまう方が意外に多いです。
そうならないように、間違えた問題をメモして次に活かしましょう。
スマホのメモアプリにメモして常に見れるといった状態にしておくと、移動時間や隙間時間に確認できるのでおすすめなやり方です。
それと合わせて、自分がなぜその問題を間違えたのか理解しておくとさらに記憶の定着率が上がります。
本番で必ず正解できるように間違えた1問1問を徹底的に見ておきましょう。
SPI非言語分野を解く3つのコツ

SPIの非言語は難しいと言われているので、ここでSPI非言語分野を解く3つのコツを理解して本番に臨みましょう。
1.単純な問題に時間をかけない
繰り返しになりますが、SPIは時間との勝負です。
そこで実際に、どのくらい言語分野の問題数と制限時間があるのか見てみましょう。
▼言語分野の制限時間と問題数
| テスト形式 | 言語 |
| Webテスト | 41問(12分) |
| ぺーパーテスト | 40問(30分) |
| テストセンター | 非言語・言語合わせて(35分) |
1問に対して大体30秒から50秒あたりで問題に解く必要があります。
そのため、1問に対して時間を割かないようしましょう。1問に対して大体30秒から50秒あたりで問題に解く必要があります。
2.推論など複雑な問題に時間をかける
何度も言うように、SPIは問題数が多いので計算で解けるような単純問題に時間を掛けすぎると、推論などの問題を解く時間が取れなくなってしまいます。
推論の問題ではどういう感じで出されるか以下で例を見てみましょう。
▼推論の出題例
【Study_Pro】(SPI).png)
参照元:「SPI無料学習サイト」
このように少し複雑で、計算すれば解けるといった問題ではありません。
ここに多くの時間を費やせるよう、サクッと答えられるような問題は時間を掛けずに解いていきましょう。
3.計算力をつけておく
何度も言うように、SPIは問題数に対しての制限時間が非常に短く、非言語分野で出題される問題全てを解くには計算力をつけておく必要があります。
計算をスピーディーにできないと1問に対して時間をかけ過ぎてしまい、全く解けないなんてこともあり得ます。
そこで、計算力をつけるにはとにかく問題を解きまくって慣れて、正確かつ早く解けるようになるしかありません。
しかし、一切計算に触れなくなると解くスピードが遅くなるので、毎日計算問題を挟むといいですよ。
電卓を使えば計算ミスを減らしてくれる一方で、普段から慣れていないとかえって時間ロスになってしまう部分もあるでしょう。
SPI全く解けないから抜け出す3つの対処法

SPIが全く解けない状態から抜け出して、内定に近づきましょう。
1.どの受検形式が苦手なのかを調べる
受検形式によって、マークシートで行う場合もあります。
そうなると、マークシートに慣れていないと答える箇所がズレたりして時間を取られ、全然できなかったということが十分にあり得ます。
そこで、先ほどもあげた受検形式のそれぞれの特徴を見てみましょう。
- Webテスト
自宅のパソコンなどを使って受検することになります。
試験では、1問に対する制限時間があり制限時間が過ぎると次の問題に移っていく仕組みになります。
受検者の正答率によって出題される問題の難易度が変化していく形式です。
他の形式と異なって、電卓を使用することが可能になっています。 - ペーパーテスト
マークシートで回答していく方式になり、電卓を使用することがは認められていません。
他の形式と異なって、全体の問題を確認してから解くことができるので、時間配分をしやすい点があります。
- テストセンター
指定された会場のパソコンで受検し、1問ごとに回答時間が定められていて回答時間が過ぎていくと次の問題が出されます。
ペーパーテストより出題範囲が多いのと、1度解いた問題に戻ることができません
電卓を使用することはできなく、会場でもらう計算用紙を使用して計算していくことになります。
そして、1年以内であれば結果の使い回しができるようになっています。
しかし、SPIの点数を知ることができないので、自分の自身のあったものを企業に提出するかありません。
このように、受検形式によって電卓の使用の有無やパソコンかマーク式かなどの違いがあることが分かったと思います。
やはり、人それぞれパソコンの操作があまり慣れていないなど苦手なことはあるでしょう。
そのため、どの形式が苦手かを把握して対策できるところは対策しておくといいですよ。
2.時間がかかる単元を特定する
ここまで見てきて、SPIは時間との勝負ということを理解できたと思います。
時間内に全ての問題を解き終えるには、時間がかかる単元を特定して少しでも早く解けるようにしていくしかありません。
どのように時間がかかる単元を特定するのかというと、問題ごとに時間を測ってどのくらいかかったかというのを把握していく必要があります。
時間がかかってしまう単元については、集中的に問題の演習をこなしていき少しでも早く解けるようにしましょう。
3.紙の参考書以外の勉強も取り入れる
紙の参考書で勉強すると、問題に慣れたり問題の傾向や問題の解き方を知ることができるのでとてもいいです。
しかし、だんだん解いていくと答えを覚えてしまったりするので、あらゆる問題を解くためにアプリやサイトでも勉強して数をこなしていきましょう。
また、1問ごとに制限時間が設けられている受検形式があるので、その形式にも慣れる必要があります。
以下の図のように、赤枠部分で制限時間が表示されるので、時間を意識して実践演習ができる学習サイトがあるので利用しましょう。
【Study_Pro】(SPI)-1.png)
参照元:「二語の関係出題例」
こちらにSPI対策ができるサイトとアプリをまとめたので、演習量そして受検形式に慣れるために駆使していきましょう。
- SPI対策アプリ(数をこなせる)
SPI言語・非言語 一問一答-Android
SPI言語・非言語 一問一答-AppleStore - SPI対策サイト(受検形式に慣れる)
SPI無料学習サイト
SPIが全く解けないならば、SPIが必要ない企業を受けよう!
ということで、まとめですが、SPIが全く解けないならば、無理せずSPIのない企業を受けるのも一つの戦略です。
そして「SPI試験無しでも、内定がもらえる優良企業」を見つけるためには、就活エージェントを使えばいいでしょう。
就活エージェントの「MeetsCompany」などを使うことで、下記全てをサポートしてくれます。
⬇︎就活エージェントがやってくれること
- 自分の希望に合う、優良企業だけをピックアップしてくれる。
- 多くの紹介企業は、ヘビーなSPIや書類選考が必要ない
- 基本的には評判の悪いブラック企業は紹介されない。なぜならエージェントにとっても信用が大事なため。
- あなたの自己分析を手伝い、あなたに合いそうな業界選び・分析をサポートしてくれる
- エントリーシート作成、面接対策など、内定に向けて必要なことを手伝ってくれる→結果として、就活エージェントを使えば、数週間〜1ヶ月で、内定をもらえることも多いです。
色々サポートしてもらえて、無料なら使わない理由はないはずです!ぜひ、企業選びのために「MeetsCompany」は活用してみてください!
毎年多くの就活生に利用されているほど大人気で、すぐに日程が埋まってしまうので、今すぐ予約を確定しましょう! ↓
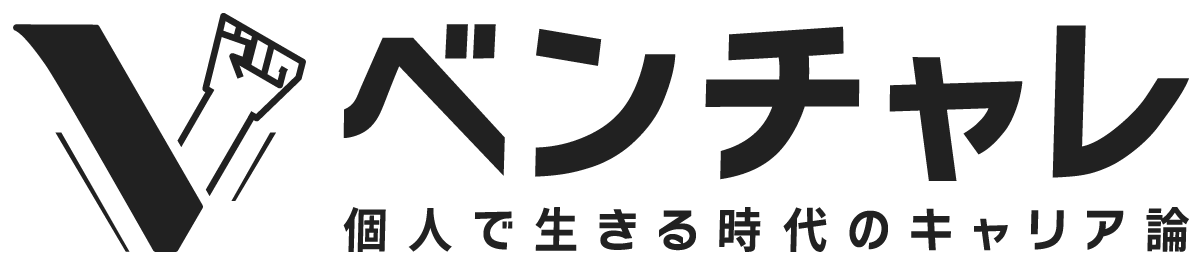
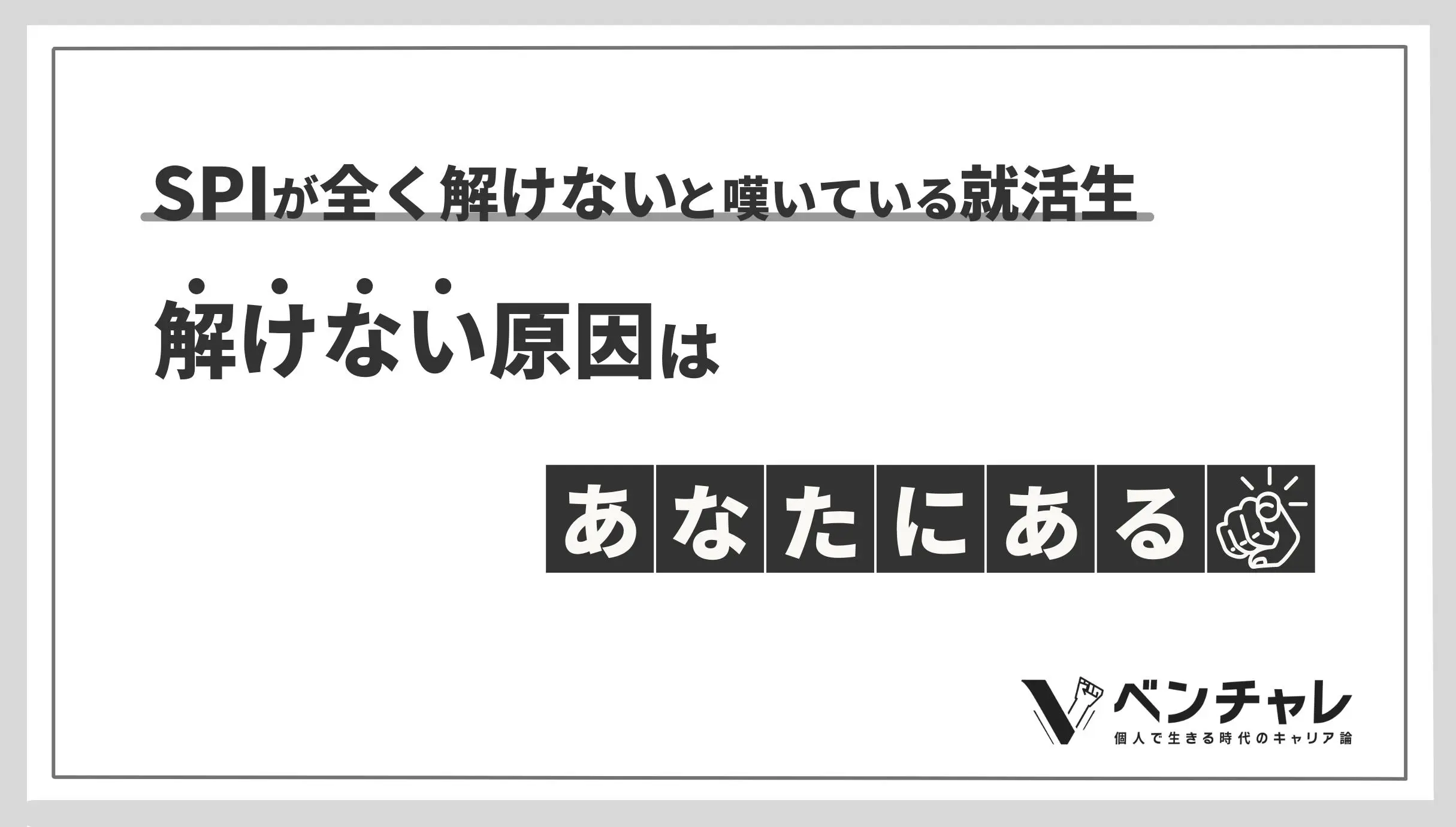
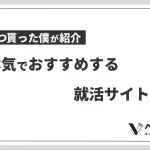
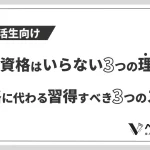
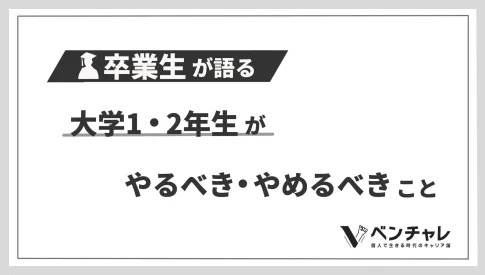
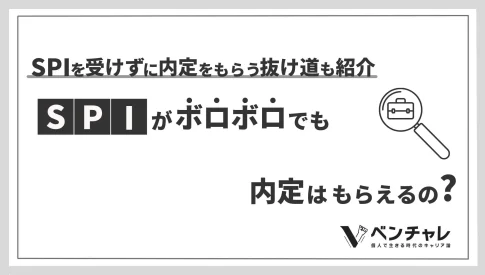

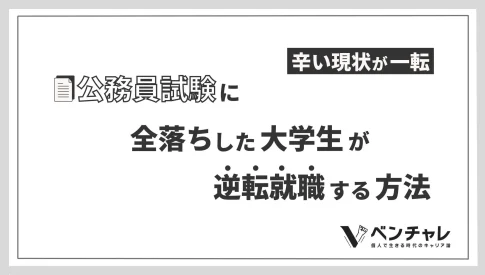
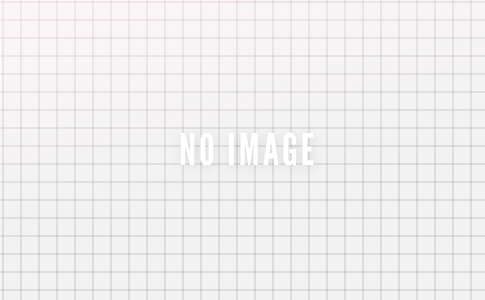
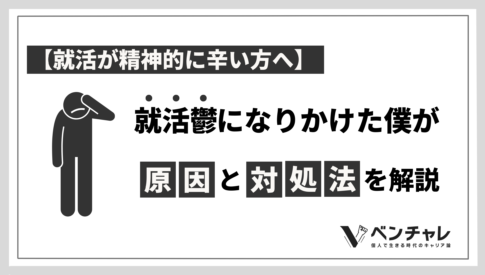
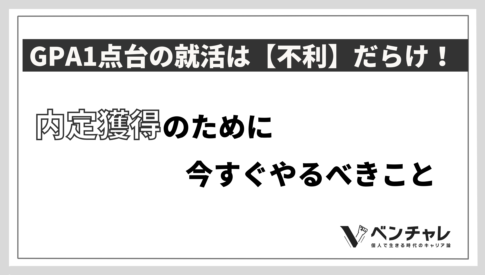
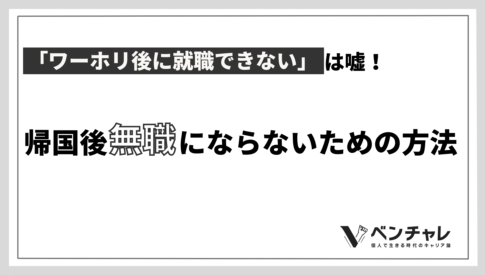
僕自身、最終的には外資系のコンサルティングファームや、大手商社から内定を貰うことができましたが、就活を始めた3月ごろ、SPI試験はほぼ全滅でした。
なぜなら、十分な対策をしてませんでしたし、3月以降になって本気で対策しても、もう遅かったからです。